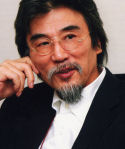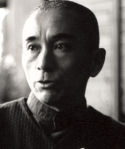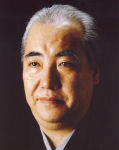|
|
特別企画 シンポジウム |
|
|
今回が4回目の開催となる文化庁舞台芸術国際フェスティバルの特別企画。目に見えるもの、見えないもの、感覚などあらゆるものの「境」をこえることを、いろいろな角度から検証していく試みです。松岡正剛氏をコーディネーターに、そしてさまざまなジャンルで活躍する芸術家の錚々たる顔ぶれが集い、活発な討論が展開されます。 |
|
| 【出演者】 | |||
|
●松岡正剛 (コーディネーター) ●天児牛大 ●梅若六郎 ●木佐貫邦子 ●高田みどり ●勅使川原三郎 ●毛利臣男 (以上、五十音順) 2005年9月19日(月・祝)6:00開演(5:15開場) 主催:文化庁舞台芸術国際フェスティバル実行委員会 |  | ||
| 【出演者プロフィール】 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||