オペラ公演関連ニュース
オペラ『ボリス・ゴドゥノフ』リハーサル開始・コンセプト説明レポート
新国立劇場25周年記念公演・ポーランド国立歌劇場共同制作『ボリス・ゴドゥノフ』のリハーサルが始まりました。リハーサル開始にあたって、出演者に向け、演出家でポーランド国立歌劇場芸術監督のマリウシュ・トレリンスキからコンセプト説明が行われました。
大野和士芸術監督は挨拶で「『ボリス・ゴドゥノフ』はご承知の通り、1600年頃のロシアの動乱時代が舞台です。イワン雷帝の死去後の後継者問題の中でボリス・ゴドゥノフが即位するものの、その後も1613年のロマノフ朝成立まで動乱が続く訳です。私とトレリンスキ氏はずっと話してきたのですが、この作品に描かれている動乱の時代、僭称者が現れるということ、権謀術数、夥しい、あるいは密やかに行われる殺戮といったこと、こういうことはどうでしょうか、私たちの世界を照らしていないでしょうか。これが私たちの創作のテーマなのです」「この作品に通底しているのは、人間に対する大きな問いかけです。そこを掘り下げたい」そして「とても大掛かりで刺激的な舞台になることは間違いない」と情熱的に語りました。

トレリンスキによる演出コンセプト説明の様子をご紹介します。

この度ここでこの非常に美しいオペラに携わることができて、大変うれしく思っています。日本へ来るのは、15年程前に映画の関係で来日して以来、2回目です。
私が『ボリス・ゴドゥノフ』に取り組むのは4回目となります。今回はムソルグスキーのこの美しいオペラを、戦争という状況下で演出することになりました。これは大変難しいことです。しかし私はできる限り、『ボリス・ゴドゥノフ』を"戦争"というテーマからは距離を置いて創りたいと考えています。そしてこの作品を掘り下げて、シェイクスピアのようなストーリーに仕上げたいと考えています。『ボリス・ゴドゥノフ』には非常に力強く興味深いキャラクターが沢山出てきます。そして現実に起こっている出来事というより、ボリス・ゴドゥノフの頭の中で起きていること、モノドラマとして描きたいと思っています。ストーリーはロシアの歴史に基づいている訳ですが、皆さんは今ここに生きている人物として演じてください。
舞台には沢山の立方体、キューブがあります。色々なシーンでこのキューブが動き、映像が映し出されます。こうしたキューブは、皆さんご存じのルービックキューブのように、常に動き回って形が変化します。それがゴドゥノフの心理をメタファーとして反映するという風に描きたいと思います。

ゴドゥノフは国が危機に陥っている中で、ある決定的な選択をします。権力を握るため先帝の息子ドミトリー皇子を殺害すること。それによって国が救われると信じています。しかし彼はこの行為への罪悪感に耐えられず、強いPTSDに悩まされます。ウグリッチで犯した殺害行為の幻影に苦しむのです。
それまで強く確固たる決意を持った男であったのに、これがきっかけとして、妄想に悩まされる男に変貌してしまいます。誰をも信じることができず、自分を支持する政治家たちや同僚、さらに娘のクセニアまでを攻撃するようになっていきます。
このストーリーは、彼の狂気を観察する物語です。彼の人間としての弱さ、そしていかなる代償を払おうとも権力にしがみ付こうとする様が、主人公の視点で語られます。我々は彼の主観的な、歪んだ世界の中に入り込んでいくことになります。
第1幕、第2幕ではゴドゥノフが徐々に狂っていく様が描かれます。彼が行った皇子殺害という行為、その代償が狂気となって自らにのしかかっていきます。戴冠式は勝利の瞬間でもありますが、同時に新皇帝の精神が衰弱していく、その始まりでもあるのです。

私たちの解釈において、決定的に重要なのが父ゴドゥノフと息子フョードルとの関係です。ゴドゥノフの後継者たるべき息子フョードルは身体に障害があり、常に介助を必要とします。ゴドゥノフは、自らの罪によって息子が病んだ、それは自らの殺人行為へ下された罰であると思い込んでいます。父は息子の姿に苦悩させられ、息子を通して、殺した皇子の幻影が見えてしまいます。ストーリーが展開するにつれ、フョードルは徐々に悪夢的な人物として存在感を増していき、ゴドゥノフを裁く判事のような存在になります。
フョードルのキャラクターは聖愚者役と融合させ、ポーランドでオーディションをして選んだ素晴らしい女優に演じてもらうこととしました(※)。聖愚者(ユロージヴイ)という人物はロシア文化において非常に重要な存在です。何でも言える特権を与えられている人物です。二面性があるのですが、ゴドゥノフに対して憐れみを表明することもあれば、同時に攻撃する人物でもあります。彼はゴドゥノフを裁く裁判官でもあり、死刑執行人でもあり、犠牲者でもあります。
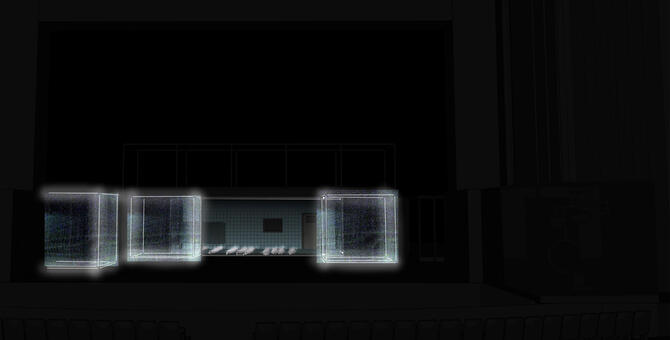
ゴドゥノフの政敵がピーメンです。私たちはピーメンを通常とは異なる解釈で描きます。彼は聖職者でありながら民衆を欺いて、宗教的な原理主義集団であり、軍事組織でもあるセクトを率いています。彼らの目的はゴドゥノフを転覆させることであり、その目的を達するために、弟子たちをプロパガンダや宗教的な狂信によって洗脳しています。その中のひとりがグリゴリーです。彼はピーメンに操られ、自分は殺されたドミトリー皇子の生まれ変わりだと信じ込んでいます。
グリゴリーはピーメンの思うままに操られ、自身を僭称者というキャラクターに変えていきます。屍の山を越え権力を掴むという点ではこのオペラの中で二人目なのですが、ゴドゥノフの方は罪への後悔に苛まれる一方で、グリゴリーにはそのようなことはありません。人を殺すことで満足を得て、全く抵抗なく人を殺すことができます。彼はナルシストでもあり、フィナーレでは自らの正体、獣にほかならない姿を露わにします。ゴドゥノフ亡き後に権力を握る悪魔的人物は、更に酷いのです。

議員たちは、プロパガンダを行う集団として描かれます。国会は一応有権者に選ばれた議員によって構成されていますが、実際は完全に腐敗しています。この議員たちはゴドゥノフの精神が著しく弱っているという状況に気づき、彼から離れています。そしてシュイスキーが僭称者を支援するように仕向けて行き、これによって彼らは重い代償を払うことになります。僭称者は国会に入って来るや、殺戮を行います。これがゴドゥノフの悲劇の最終段階です。僭称者グリゴリーは自身の本性を表し、自らと敵対する人物に留まらず、自らを創り上げた人物、ピーメンまで殺害します。
ゴドゥノフとピーメン、政敵同士である二人はそれぞれの目的のために戦ってきたのですが、結果的に、彼らは更に酷い獣を生んでしまったということが明らかになります。この獣は良心の呵責というものを持ち合わせていません。僭称者が権力を得たことで、世の中の状況は更に悪化し、苦しみに満ちていく。これを見たゴドゥノフは、息子を僭称者の残虐な行為から守ろうとします。
最後のゴドゥノフのモノローグはオペラ史上最も美しい感動的な部分だと思います。このシーンは感情に重きを置いた演出にするつもりです。私たちがここで目の当たりにするのは、自分自身の選択の結果に苦しむ人物です。ゴドゥノフは僭称者が復讐に飢えていることを確信し、恐れ、できる限り穏やかに、息子が苦しまなくて済むよう息子の命を奪うという決断を下すのです。その直後に、ゴドゥノフ自身も残酷な処刑により殺されてしまいます。僭称者は聖杯に注いだゴドゥノフの血を飲み干します。獣がこの国を征服したのです。

「シンドラーのリスト」等数々の映画で活躍する著名ヘアメイクアーティスト

欧米の主要劇場・カンパニーの演劇、オペラで活躍、第一線の演出家たちの信頼厚い舞台衣裳家、ファッションデザイナー
こうした解釈で『ボリス・ゴドゥノフ』に取り組んでいる最中に、現実にポーランドの隣国ウクライナで戦争が始まろうとしていました。私たちは何か時代を超越した普遍的な意味があるのではないかと考えました。そして私たちはこの素晴らしい芸術作品が崩壊の過程、最も高い政治権力の内部から引き起こされる腐敗の過程を描いているということ、そしてその後には更に酷い悪が待ち受けているということを発見しました。
今回ロシアが引き起こした戦争は非常にばかげていますが、恐ろしい破壊を引き起こしています。状況は、シェイクスピアの次元すら超えていると思えます。私たちの演出は、これまでのロシアでの演出に強く結びついていたナショナリズムや帝国主義への批判となるでしょう。
私たちの『ボリス・ゴドゥノフ』はある男の物語です。邪悪で傷ついて殺人者であるマクベスのような男、そして自分自身を最も厳しく裁き、罰する男の物語です。
『ボリス・ゴドゥノフ』は11月15日(火)の開幕に向け、リハーサルが進んでいます。
オペラの現代性を発信し続けている新国立劇場から、また新たに、時代を問う新プロダクションが世界へ向けて発信されます。どうぞお楽しみに。
※本プロダクションでは、フョードル(聖愚者)役を黙役として俳優が演じ、フョードルのパートはクセニアの友人役として小泉詠子が歌唱、演技します。
また聖愚者のパートは清水徹太郎が歌唱します。
- 新国立劇場HOME
- オペラ公演関連ニュース
-
オペラ『ボリス・ゴドゥノフ』リハーサル開始・コンセプト説明レポート
